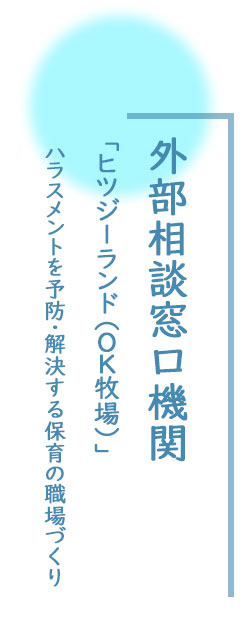
保育園におけるパワーハラスメント対策が、
令和2年6月1日から義務になりました(パワハラ防止法)
園長はパワーハラスメントを防止するため、
主に次の雇用管理上の措置を講じる必要があります(指針)
| 園長が講じる必要がある雇用管理上の措置※1 | ハラスメント予防士 養成講座 |
外部相談窓口機関 |
|---|---|---|
| ①就業規則等に方針等を規定すること | ー | ◎ |
| ②職員に資料等を配布し啓発すること | ○ | ○ |
| ③職員に研修・講習等を実施すること | ◎ | ー |
| ④相談窓口等の体制を整備すること | ー | ◎ |
| ⑤相談窓口の担当者に研修をすること | ◎ | ー |
| ⑥アンケート調査や意見交換等を実施すること | ー | ◎ |
| ⑦運用状況の的確な把握や必要な見直しをすること | ー | ◎ |
相談先をあらかじめ定めて周知し、相談窓口から主体的に働きかけることが大切です。
外部の機関に相談への対応を委託することも、体制や制度の整備として必要になります。
相談窓口の担当者は、職員の捉え方に迷う微妙な場合や相談を躊躇する場合等、
早期に柔軟に、その内容や状況に応じて広く相談に対応できるように、
相談体制や制度の必要な準備をし、相談窓口の適切な運用に努めなければなりません。
費用:園長 1名 1万円(月額)
担当者 1名 5千円(月額)
方法:オンライン
内容:ハラスメントや人間関係の園外の相談窓口になり園内の相談窓口と連携
連携例:① 毎月のセッション
② 規定の策定・変更
③ 周知資料の作成・配布
④ アンケート調査の実施
⑤ 園内の相談窓口担当者からの相談対応
⑥ 園内の職員からの緊急的な第三者対応
⑦ 相談窓口の一体的な運用と見直し
参考図書:『ハラスメントを予防・解決する保育の職場づくり』(中央法規出版)
参考資料:①「外部相談窓口機関専用のオリジナルマニュアル」
②「厚生労働省等の公的資料や各種統計データ」
外部相談窓口機関によりハラスメントを積極的に予防する目的は、主に以下です。
① 法律・法令に基づく制度等の理解・活用を促進し、ストレスや負荷の軽減につなげ、
② 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備を、外部から監視して機能させます。
③ 外からの風通しもある職場環境とし、安全安心な職場風土を醸成することで、
④ お互いに安心して意見を表明したり傾聴したりできる「心理的安全性」を高めます。
相談窓口には、以下のような機能が必要とされます(指針)。
① 広く相談に応じ、内容や状況により柔軟かつ適切に対応する機能
② 相談窓口の担当者間や園長等と連携する仕組みを運用する機能
③ 放置すれば就業環境を害するおそれを早期に対策する機能
④ 職員同士のコミュニケーションの希薄化を予防する機能
⑤ 留意点などを記載したマニュアルに基づき相談に対応する機能
⑥ 相談窓口の担当者自身や職員に対して、必要な研修を行う機能
⑦ 外部の機関に相談への対応を委託し連携する機能